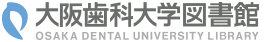16世紀
Andreae Vesalii Bruxellensis, De humani corporis fabrica libri septem
『人体構造論 7巻』
ベルギーの解剖学者で外科医のベサリウス(1514-64)は、1533年パリ大学に学び、ガレノス(Galenos)学説の講義を聞いたがあきたらなくなり、動物の解剖・人骨の収集によって解剖学を研究した。
1537年、23歳でイタリアのパドバ大学の解剖学と外科学の教授に任じられ、翌年には、友人の画家の協力を得て“Tabulae anatomicae sex”を著した。次いで1543年にバーゼルで解剖学史上最高古典といわれる本書の初版を刊行した。しかし、ベサリウスは、この書の中で中世以来のガレノスの権威に抗して自己の見解を主張したために、大方の非難をあび、ついに解剖学研究を断念した。1563年にはエルサレムに巡礼し、その帰途、船が難破してイオニア海の島で病死した。
本書の初版は、ガレノスの学説を打破して、近代解剖学の強固な基礎を確立しただけでなく、同じ年に出版されたコペルニクス(Nicolaus Copernicus)の"Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI"と並び近代科学そのものを確立した著作とされている。
書名のとおり、「骨格系」「筋肉系」「脈管系」「神経系」「内臓」「心臓・肺」および「脳・感覚器官」の7巻からなり、左右心室の完全な中隔、処女膜、胎盤を記載しているほか、胎児の血行に関してなど新知見が数多く見られる。歯については、わずか2ページの記述しかないが、これまでに度々引き継がれてきた誤りが一掃されている。
1555年に刊行された本書においては、本質的な進歩を示してはいないが、彼は「私の弟子たちや私の後に続く人々が、私の創始した実地所見に基づく人体解剖学を完成しようと努めている」と述べている。この言葉どおり、ベサリウスが示した成果と精神は、コロンボ(Colombo)、ファロピウス(Fallopius)、ファブリキウス(Fabricius)らに受け継がれた。
Libellus de dentibus
『歯についての小論』
イタリアの解剖学者で、ローマ大学教授であったエウスタキオ(1500または1514-74)は、1552年に世界で最初の銅板解剖図“Tabulae Anatomicae”を完成し、交感神経の全景や脳底の詳細な図解など多数の新知見を記したが、この図譜は1714年に出版されるまで法王宮図書館に埋もれたまま知られることはなかった。また、彼はこのほかの幾つかの著書の中でも、今日まで彼にちなんだ名で呼ばれている耳管(Eustachian tube)をはじめ、胸管や副腎の発見、交感神経系の構造の解明などきわめて多くの業績を残しており、彼の処女作が生前に公表されていればベサリウス(Vesalius)と並ぶ解剖学の創始者とされていただろうといわれている。
30章からなる本書は、歯牙の解剖について書かれた最初の単行本であり、流産児、死産児、さまざまな年齢の幼児および動物の子供を対象とした体系的な調査の成果が、歯牙の解剖・生理・発育の全般にわたり正確に記述されている。中でも、歯牙形成の研究が有名であり、歯嚢の発育を観察することにより、永久歯は乳歯の歯根から発生するというベサリウスの主張を覆した。
De aureo dente maxillari pueri Silesii, primum, utrum ejus generatio naturalis fuerit, necne; deinde an digna ejus interpretatio dari queat. Et De noctambulonum natura, differentiis & causis, eorumque tam praeservativa quam etiam curativa, denuo auctus liber
『シュレージェン地方の子供の金の臼歯に関する考察』
1593年、シュレージェン地方シュバイトニッツで下顎に金の臼歯を持つ子供が発見されたとの噂がドイツ全域に流布した。科学的根拠に基づくものではなかったが、当時はそれについて多くの論文や小論が発表された。
ドイツの医師でユリウス大学医学教授であったホルスト(1537-1600)も、本書において、この現象を子供の出生時における星座の位置関係による自然的および超自然的要素によって発生したものと解説している。
17世紀
De vocis auditusque organis historia anatomica, singulari fide methodo ac industria concinnata tractatibus duobus explicata ac variis iconibus aere excusis illustrata
『喉と耳の解剖学』
イタリアの解剖学者であるカッセリオ(1552-1616)は、ファブリキウス(Fabricius)の弟子で、パドバ大学教授であった。
本書は、2部から構成されており、蝸牛の構造などを含む耳および喉頭についての解剖学的新知見が多数の図版とともに記されている。
Anatomical exercitations, concerning the generation of living creatures : to which are added particular discourses, of births, and of conceptions, &c.
『動物の発生に関する研究』
イギリスの医学者であり解剖学者であるハーベー(1578-1657)は、ケンブリッジ大学とパドバ大学に学んだのち、ロンドン医師会の会員になった。その後ジェームズ1世とチャールズ1世の侍医となり、1645年からはオックスフォード大学マートンカレッジの学長を務めた。ピューリタン革命後は不遇となったが、若い科学者たちの支持を受け、晩年まで研究を続けた。
ハーベーは医学および生物学に実験的方法を組織的に導入した最初の人である。彼の最大の功績は血液循環論の発見であるが、発生学においても優れた研究成果をあげている。本書の原著(ラテン語)は1651年に出版されたが、綿密な観察に基づいて、ニワトリ胚が胚盤から発生すること、動物の種類にかかわらず胚期の形態はたがいに類似していること、そして哺乳類の胎児の血管系と母体の血管系の間には直接の接合がないことなどを証明している。
Traité de l'organe de l'ouie : contenant la structure, les usages & les maladies de toutes les parties de l'oreille
『聴覚器官の研究』
デュベルネ(1648-1730)は、17世紀フランスの解剖学興隆の立役者として知られている。
本書は、「耳科学の父」と呼ばれている彼の主著であり、初めて耳の病気と器官を結び付けた著作として名高い。
L'anatomie de l'homme, suivant lacirculation du sang, & les dernieres découvertes, dé montrée au Jardin Royal
『解剖学』
ディオニ(1643-1718)はパリの有名な外科医であり、解剖学者でもあった。
1707年に出版した“Cours d'operations de chirurgie”の中で、彼は外科医としての見地から歯科治療を7種に分類して詳述している。本書では、まれに二重歯列を有する人がいることなどが論じられている。
本書の初版は1690年に出版されたが、その後、英語、タタール語などに翻訳され、多くの版を重ねた。
18世紀
Le chirurgien dentiste, ou, Traité des dents : où l'on enseigne les moyens de les entretenir propres & saines, de les embellir, d'en réparer la perte & de remédier à leurs maladies, & à celles des gencives & aux accidens qui peuvent survenir aux autres parties voisines des dents : avec des observations & des réflexions sur plusieurs cas singuliers
『歯科外科医』
フォシャール(1678-1761)は、フランスにおける歯科学の先駆者であり、近代歯科医学の祖であって、「歯科医学の父」と呼ばれている。また歯科医業の創設者としても名高い。
ブルターニュに生まれ、若い時代に海軍の外科医生として外科の基礎を学ぶとともに壊血病などの口腔疾患の治療を経験した。19歳のときアンジェ市で自ら造語したChirurgien-dentiste(歯科外科医)を標榜して開業し、その本格的な医術により名声を博した。40歳でパリに進出した後、長年にわたる膨大な臨床記録をまとめて1728年に出版したのが、世界で最初の本格的な歯科医学書である本書であった。
本書は、近代歯科医学史上の名著パッフ(Philipp Pfaff)の“Abhandlung von den Zahnen(1756)”およびハンター(John Hunter)の“The natural history of the human teeth(1771)”に先行する重要な著作であり、それ以前には秘術・秘法とされていた歯科治療法を初めて明らかにした書として知られている。
18世紀初期の定説を基に、豊富な最先端の治療を織込んだ独創的で的確な内容は基礎から臨床に及んでおり、最高の歯科医学書と称賛されて、一挙に外科歯科医の地位を高めた。また、医学関係の教科書としてドイツをはじめ欧州各地で翻訳されて大きな影響を与え、歯科医学の急速な発展を促すとともに、歯科学を医学的基盤に立つ独立した存在として認識させるきっかけをつくった。
Französischer Zahn-Artzt, oder Tractat von den Zähnen: Worinnen die Mittel, selbige sauber und gesund erhalten, sie schöner zu machen, die verlohrne wieder zu ersetzen, und die ungesunden, wie auch die Kranckheiten des Zahnfleisches, und die Zufälle, welch anderen nahe bey den Zähnen liegenden Theilen zustossen können, zu heilen, gelehret werden. Samt Observationen und Betrachtungen über viele besondere Fälle
『歯科外科医』
本書は、フォシャール(1678-1761)の名著“Le chirurgien dentiste”のドイツ語訳であり、原著刊行後わずか5年で出版されていることからも、原著が専門分野の人々に与えた影響の大きさが伺える。
プロシアの解剖医であり、枢密顧問官であったブッダオス(August Buddaus)による序文が付けられている。
Practical treatise upon dentition : or, The breeding of teeth in children : where in the causes of the acute symptoms arising in that dangerous period are enquired into : the remedies both of the ancients and moderns for the cure of those evils, and the prevention of their fatal effects, are examined impartially : some errors of consequence corrected : objections answered : and a right practice recommended upon observation and experience : the whole illustrated with proper cases and remarks
『生歯の実際的研究』
ハーロック(1675-1742)はロンドンの外科医である。彼は本書において、自らの治療経験と専門家の著作からの引用によって、生歯による子供の死亡を防ぐためには、生えてくる乳歯のために歯肉を切開することが唯一の有効な手段であると主張している。そして、この著作の影響から、イギリスでは19世紀にいたるまで、歯肉の切開こそが典型的な治療法であった。
本書は小児歯科に関する最初の著作といわれている。
Essay sur les maladies des dents, ou L'on propose les moyens de leur procurer une bonne conformation des la plus tendre enfance, & d'en assurer la conservation pendant tout le cours de la vie : avec une lettre ou l'on discute quelques opinions particulieres de l'auteur de l'orthopedie
『歯の病気について』
Dissertation sur un préjugé très pernicieux, concernant les maux de dents qui surviennent aux femmes grosses
『歯の病気に関する偏見について』
フランスの歯科医ビュノン(1702-48)は、北フランスやフランドル各地で歯科の知識・技術を習得したのちパリに居を定めた。1741年にある新聞紙上に初めて論文を発表して以来、1744年までの間に歯科医学に関する4つの重要な著作を発表している。彼は、特に歯の発育不全について研究しており、歯の健全な育成に必要な衛生状態や、最初に生える乳歯とその病気の重要性を強調している。
本書にはビュノンの2つの著作が収められているが、前半の論文は、自らの研究成果を集大成したものであり、1746年には増補改訂版が出されている。また、後半は、妊婦の歯科治療に関して、当時一般に信じられていた迷信を科学的根拠を示すことによって否定しており、その見解は、フォシャール(Fauchard)の著書“Le chirurgien dentiste. 2nd ed.”に紹介され賛同を得ている。
Nouveaux éléments d'odontologie : contenant l'anatomie de la bouche ; ou la description de toutes les parties qui la composent, & de leur usage; & la pratique abregée du dentiste, avec plusieurs observations
『新歯科学要論』
フランス人のレクルーズ(1711-92)は、歯科医としてだけでなく演劇や詩文学などさまざまな分野で活躍した人である。
本書では、乳歯をできるだけ保存することを解いた卓見を述べている。また、新しい抜歯用具、特に下顎の智歯を抜くための彼独自の道具について言及しているが、今日の歯科用エレベーターのすべてにこの道具の原理が用いられている。
Recherches et observations sur toutes les parties de l'art du dentiste
『歯科医学の研究と観察』
ブールデ(1722-89)はフォシャール(Fauchard)以降のフランスの歯科学において最も重要な歯科医である。南フランスのアジェンで生まれた彼は、パリに出た後、1760年に宮廷付きの歯科医になった。彼は補綴術、特に義歯床を従来の口蓋や鼻内ではなくクラスプを用いて歯に固定する技術を開発するなど歯科医学の発展に大きく貢献した。
本書は、ブールデの主著であり、全体の構成などは、彼が「道を開いてくれた人」と呼ぶフォシャールの影響が著しいが、さまざまな点で偉大な模範をしのいでいる。豊富な経験と観察力をもとに、歯の構造や衛生、病気の予防や新しい治療法などの歯科医に必要とされる知識や技術を体系的に解説しており、高い評価を得た。
Soins faciles pour la propreté de la bouche, et pour la conservation des dents ; par M. Bourdet, Chirurgien-dentiste. Suivis de L'art de soigner les pieds, contenant un traité sur les cors, verrues, durillons,oignons, engelures, les accidens des ongles & leur difformité
『歯と口腔の衛生』
本書は、ブールデ(1722-89)が専門家よりむしろ一般大衆向けに出版した著作である。食事と歯の健康との関連、歯垢の予防と除去、齲蝕、歯周疾患、義歯の使用など歯科衛生に関する項目が、多くの実験と綿密な観察に基づいて解説されている。初版刊行当時、大変な好評を博し多くの版を重ねた上、1762年にドイツ語版が、1773年にはイタリア語版が出版されている。
Traités des dépôts dans le sinus maxillaire des fractures, et des caries de l'une et de l'autre machoire, suivis de réflexions et d'observations sur toutes les operations del'art du dentille
『上顎洞膿瘍に関する研究』
パリに生まれたジュールダン(1734-1816)は、博愛精神から外科医になり、神学校で研修を積んだのち、歯科医に転じレクルーズ(Lecluse)の弟子となった。彼は、フォシャール(Fauchard)、ブールデ(Bourdet)と並ぶ著名な歯科医でもあったが、より広範に、口腔および顎周辺の病気の研究に専念した。
本書は、彼の処女作であり、ハイモール洞蓄膿症および上下顎における骨傷、折損に関する治療法などを論じている。
Jourdain, Anselme Louis Bernard Bréchillet Traité des maladies et des opérations réellement chirurgicales de la bouche, et des parties qui y correspondent : suivi de notes, d'observations &de consultations inté ressantes, tant anciennes que modernes
『口腔疾患と外科手術』
本書はジュールダン(1734-1816)の主著で、上巻では上顎の疾患、下巻では下顎の疾患について述べているが、専門歯科技術だけでなく、広く口腔の疾患を扱い、その後長くにわたって価値を認められてきた。何度も再版された上、1784年にはドイツ語版が、また半世紀以上たった1849年にはアメリカで英語版が出版されている。
A treatise on the disorders and deformities of the teeth and gums : explaining the most rational methods of treating their diseases : illustrated with cases and experiments
『歯と歯肉の疾患と奇形』
バードモア(1740-85)はイギリス最初の高名な歯科医であり、ジョージ3世の侍医を務めた。
また、彼は、その著作だけでなく専門医をめざす多くの医学生に理論的、実践的鼓舞を行うことによってイギリスにおける歯科医学の進歩に寄与した。
本書は増補新版であるが、初版(1768年)刊行当時から好評を博して多くの版を重ね、1769年にはオランダ語に、1771年にはドイツ語に翻訳され、さらに1844年にアメリカで復刻されている。
The natural history of the human teeth : explaining their structure, use, formation, growth, and diseases
『人の歯の博物学』
A practical treatise on the diseases of the teeth : intended as a supplement to the natural history of those parts
スコットランドに生まれたハンター(1728-93)は、ロンドンで解剖学を学び、さらに外科学を修めたのち、ジョージ3世(George III)付きの外科医となり、聖ジョージ病院で外科学を講義した。その独創的な観察と研究は、炎症・血液・創傷・性病など基礎から外科臨床の多方面に及んでおり、「実験病理学の祖」とも呼ばれ、イギリスの外科学を内科学と同等の学問分野にまで高めた。また収集癖が強く、比較解剖学の研究に用いた動物標本は1万3000点に達する。晩年には軍医総監に任ぜらたが、淋病と梅毒の病原体解明のため、自身に人体実験し、自らの実験の犠牲者となった。
門下生であったジェンナー(Edward Jenner)が教えを乞うたとき、「But why think ? Why not try the experiments ?(考えるより、試みよ)」と助言したという。
ハンターは、エウスタキオ(Eustachio)以後科学的な方法で歯科学を研究した最初の人物として、近代歯科医学にも大きな影響を与えた。
本書の初版(1771年)は、歯と口腔の解剖を科学的に体系づけた最初の口腔解剖学書であり、それまでは単に経験的な方向付けしかなかった歯科医学に新しい学問的な道を切り開いた。この第2版では、“The natural history of the human teeth”に“Practical treatise on the diseases on the teeth”の初版を加え、歯科医学の基礎と臨床を総合して展開している。
19世紀
The natural history of the human teeth : including a particular elucidation of the changes which take place during the second dentition, and describing the proper mode of treatment to prevent irregularities of the teeth
『人の歯の博物学』
The history and treatment of the diseases of the teeth, the gums, and the alveolar a processes : with the operations which they respectively require ; to which are added, observations on other diseases of the mouth, and on the mode off ixingartificial teeth
『歯科疾患治療の歴史』
ハンター(John Hunter)の弟子であるフォックス(1776-1816)は、医学生に歯科医学を正規に講義した最初の人である。彼は、1797年にロンドンのガイ病院に初めての歯科外科医として採用され、医学生に特別教科として歯科医学を講義した。それらの講義を編纂・出版したものが本書の後半に収録されている"The history and treatment of the diseases of the teeth"である。
本書は、歯科手術、特に歯列矯正に関して先駆的な役割を果した著作として知られており、いわゆる乱杙歯やその矯正に使用した革製のヘッド・チンキャップなどの器具が描かれた図版が含まれている。本書で述べられた学説は19世紀前半の歯科矯正術に決定的な影響を与えた。
Traité des maladies de la bouche; d'après l'état actuel des connoissances en médecine et en chirurgie, qui comprend la structure et les fonctions de la bouche, l'histoire de ses maladies, les moyens d'en conserver la santé et la beauté, et les opérations particulières à l'art du dentiste
『口腔の疾患』
ガリオ(1761-1835)はパリの歯科医であり、世界最初の咬合器の考案者である。
本書には、彼が考案した簡単な石膏咬合器のことや彼が印象型を採り、熟練した職人が作製した義歯のこと、そして銅箔、銀箔および金箔を使用した充填法などが記されている。
Traité de la première dentition et des maladies souventtrès graves qui en dépendent; ouvrage que la Société royale de médecine de Paris couronna en 1782, et dans lequel on trouve la meilleure manière de conduire et d'élever lesenfans de naissance
『第1生歯と疾患』
狭心症の「ボーメ症状」で知られるフランスの病理学者ボーメ(1756-1828)は、多年にわたりモンペリエ大学の教授として教鞭を執り、熱病・小児病・肺結核のほか疾病分類学や瘰癧など医学に関する数多くの著作を執筆した。
本書は生歯障害とその治療に関する論文で、1841年には英語の翻訳版が出されている。
Le manuel de l’art du dentiste, ou, L’État actuel des découvertes modernes sur la dentition : les moyens de conserver les dents en bon état : les mécaniques nouvelles inventées par M. Maggiolo : et tous les détails pratiques et moyens d’exécution des dents artificielles, etc
『歯科技術の手引』
ナンシーの歯科医であるマッジオロ(1734-1816)は、本書において歯科医療技術に関する新しい発見や発明について述べているが、その中のひとつとして自ら考案した義歯を固定するための止めバネ式ポスト(合釘)を紹介している。
Traité de la partie mécanique de l'art du chirurgien-dentiste
『歯科技術の機械的側面に関する考察』
デラバール(1787-1862)は、フランスの宮廷歯科医であり、科学的義歯教本を書いた最初の人である。
本書では、陶歯の改良、局部義歯の鉤による固定、口蓋帆の補綴など種々の補綴術について論じているほか、印象採得法を改良するためトレーの採用を推薦して、歯科医療技術の発展に貢献した。
A practical guide to operations on the teeth : to which isprefixed a historical sketch of the rise and progress of dental surgery
『歯科手術の実際』
スネル(1795?-1850)はロンドンの歯科医である。
本書では歯科手術の進歩を概観したのち、抜歯術や術後処置のほか手術用器具についても記しており、口絵には自らが考案した光沢のあるスチール製の歯鏡を付けたデンタルチェアの図を載せている。
A popular treatise on the teeth and gums and diseases attendant on them : designed for the use of families
『歯と歯肉およびその病気について』
本書は、専門家のためにではなく、各家庭における手引書となることを目的に執筆された著作で、19世紀初頭の歯学書の中でも最も珍しいもののひとつである。大英図書館にも所蔵がなく、National Union Catalogueでもわずか3か所の所蔵しか確認されていない。
Le dentiste des dames
『婦人の歯科医』
フランスの宮廷歯科医であったルメール(1782-1834)は、誕生から老年にいたるまでの口腔ケアの重要性を論じた人であり、歯を強く美しく保つための方法を研究した。
本書は、婦人のための歯の衛生に関する論文で、1812年に出された初版の増補新版である。
Researches on the Development, Structure, and Diseases of the Teeth
『歯の発達・構造・病気の研究』
ロンドンのRoyal College of Surgeonの一員であった歯科医で解剖学者のナスミス(1789-1848)は、歯小皮の発見者として知られている。彼は1839年にRoyal Societyに1点の組織を提出した。これは今日われわれが歯小皮とかエナメル小皮と呼んでいるものであったが、彼は本書の中で、ある種の哺乳類に見られる歯冠セメント質への類推のもとに、この膜をセメント質がエナメル質を覆っている部分が退化した痕跡であると解釈した。彼が発見した歯小皮は、今日でもナスミス膜(Nasmyth cuticle)と呼ばれている。
Odontography; or, A treatise on the comparative anatomy of the teeth; their physiological relations, mode of development, and microscopic structure, in the vertebrate animals
『歯型図録あるいは歯の比較解剖学』
ロンドンの解剖学者オーウェン(1804-92)は、Royal College of Surgeonsの教授であり、1856年からは大英博物館の自然史部門の部長を務めた。また、彼はハンター(John Hunter)の蒐集物の管理者でもあって、遺品を整理しカタログを著している。
本書は、歯に関する比較解剖学書であるが、その中で、彼は今日もなお一般に用いられている「象牙質、エナメル質およびセメント質」という表現を用いている。ちなみに「象牙質」という名称は彼が考え出したものとされている。
Nouveau traité théorique et pratique de l'art du dentiste
『新歯科技術の理論と実際』
フランスの歯科医であるルフロン(1800-?)は、本書で、臨床経験に基づいた多方面にわたる新しい治療技術を紹介している。歯列矯正から顎の矯正へと歩みを進めていた彼は、歯間狭窄の矯正のために、弾力性のある金製の弧状金具を歯列の内側に装着する方法を考案した。
本書の中で、彼は、自らが発明したこの歯列内側用弧状金具について記述した章を“Orthodontosie”と名付けている。
A course of lectures on dental physiology and surgery, delivered at the middlesex hospital school of medicine
『歯の生理学・外科学講義』
トームス繊維(Tomes' fiber)、トームス顆粒層(Tomes' granular layer)、トームス突起(Tomes' process)などの歯牙組織構造の発見者として有名なトームス(1815-95)は、「イギリスにおける現代歯科医学の父」といわれている。彼は、最初薬剤師のもとで修業し、1836年以降はロンドンのキングスカレッジ等で医学を学び、1840年に歯科医となった。その後、歯の構造に関する研究を行って成果をあげ、キングスカレッジに歯科医学者として迎えられると同時に開業して、組織学の研究に没頭した。ウィルヒョウ(Rudolf Virchow)に古典的名著と評された本書のほか数種の著作を発表したのち、生涯の最後の30年間をイギリスにおける歯科医師の地位の向上と制度化に捧げた。歯科医師の資格認定制度の確立、歯科医師法の立法化、イギリス歯科医師会の創設等の彼の活躍に対し、1879年にはイギリス歯科医師会の初代会長に選出され、1886年には貴族の称号を与えられた。
本書は、彼がミドルセックス州病院で学生に行った講義を収録したもので、歯科医師用教科書の古典として評価が高い。
A treatise on the diseases and surgical operations of the mouth, and parts adjacent : with notes of interesting cases, ancient and modern.
『口腔疾患と外科手術』
ジュールダン(1734-1816)の主著“Traite des maladies et des operations reelement cirurgicales de la bouche”の英語翻訳版である。
本書の出版は、原著初版の出版から数えて71年めのことであり、このことからも原著の価値の高さが伺える。英語翻訳版は1851年にも再版されている。
A system of dental surgery
『歯科学体系』
本書は、イギリスの歯科医トームス(1815-95)の著作で、彼が考案した歯科用高速回転切削器などの歯科器具や設備が記された純然たる実用書である。1861年にはそのドイツ語訳が、1873年にはフランス語訳が出版され好評を博した。
A dictionary of dental science, biography, bibliography, and medical terminology
『歯科学辞典』
ハリス(1806-60)は、ニューヨーク州に生まれ、初め兄ジョン(John Harris)のもとで医学を修めたが、1827年頃には歯科医学に興味をもち、のちに歯科専門医となりボルチモアで開業した。また、彼はハンター(John Hunter)、フォックス(Fox)およびデラバール(Delabarre)の著書を熱心に研究したほか、フランスの歯科医学者たちの著作を次々と翻訳して出版した。1839年には、ニューヨークの歯科医パームリー(Eleazar Parmly)と協力して世界で最初の歯科医学雑誌“The American Journal of Dental Science”を創刊し、その主幹として同誌を全国的な規模に拡大した。翌40年には、ハイデン(Horace H. Hayden)と協力して世界初の歯科医学校であるBaltimore College of Dental Surgeryを創立し、ハイデンの死後第2代校長となった。また、1841年には、ハイデンを助けて、世界で最初の歯科医師の専門団体としてアメリカ歯科医師会を結成して、その組織の確立に尽力した。
本書は、初版刊行後50年間に5版まで出版された。
The principles and practice of dental surgery
『歯科医学の理論と実際』
本書は、アメリカの歯科医ハリス(1806-60)の著作である。最初、1839年に“The dental art, a practical treatise on dental surgery”の書名で出版され、1845年の第2版で内容を倍に増補して、上記の書名に改題された。当時の歯科医学の代表的な教科書であり、1896年までに実に13版まで出版され、また多くの国の言語に翻訳された。その結果、あらゆる教科書の中で最もポピュラーなもののひとつとなった。明治時代の日本にアメリカの歯科医学が伝わると、ハリスの著書を稿本として邦訳が刊行された。
Report to the House of Representatives of the United States of America, vindicating the rights of Charles T. Jackson to the discovery of the anaesthetic effects of ether vapor, and disproving the claims of W.T.G. Morton to that discovery : presented to the House of Representatives of the United States, on the 28th of August, 1852
『アメリカ合衆国下院報告 : エーテルの蒸気麻酔発見に関するジャクソンの権利とモートンの反駁』
モートンは、1840年からボルチモアで歯科医学を学び、さまざまな試行錯誤ののち1846年9月に初めてエーテル吸入法による麻酔で無痛抜歯に成功した。これは医学における偉大な発見のひとつであり、すぐに外科手術にも応用された。彼は同年11月に“Letheon”の名称で特許を得たが、それに対し共同研究者であったジャクソン(Charles Thomas Jackson)らが反論を唱え、第一発見者をめぐる論争が起こった。フランス科学アカデミーの調査の結果、ジャクソンには麻酔法の発見に対して、モートンには麻酔法の外科治療への応用に対して双方に2500フランの賞が贈られた。しかし、この論争によってジャクソンのボストンでの事業は破掟を来たしたため、彼は救済措置として議会に報奨金を申請している。
Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre : zwanzig Vorlesungen, gehalten während der Monate Februar, ...
『細胞病理学』
ウィルヒョウ(1821-1902)は、ドイツの病理学者、人類学者で、細胞病理学を確立したことにより「近代病理学の祖」といわれる。また社会医学、公衆衛生の面でも業績を残し、政治家として医学と政治を結び付けた活動を行ったことでも知られている。28歳の若さでビュルツブルク大学の病理学、病理解剖学の正教授となり、1855年細胞病理学説(Cellularpathologie)を唱えて、病気を体液の異常にのみ置く古代からの病理観を一新した。翌年にはベルリン大学に迎えられ、2年後に主著である本書を出版した。
本書は、1858年の2月から4月にかけて、ベルリン大学で臨床医を対象に行われた20回の講義をまとめたものであり、口述体で書かれている。全22章からなり、生体の器官、組織は究極的には細胞の集合体であり、その病変はすべて細胞に基因するという考え方に立って論じられており「Omnis cellula e cellula(すべての細胞は細胞から)」という言葉は有名である。
本書はその後も続いて増補改版されるとともに、5ヵ国語に訳されて、世界の新しい病理学の指導的教科書となった。卓越した知見と深い洞察に満ちた本書の真価は現代でも失われていない。
On the origin of species : by means of natural selection, or thepreservation of favoured races in the struggle for life
『種の起源』
イギリスの生物学者で進化論の確立者であるダーウィン(1809-82)は、エジンバラ大学の医学部およびケンブリッジ大学の神学部に学び、この間、博物学者たちとの交友を通じて生物学と地質学に興味をもった。1831年、海軍の測量船ビーグル号に乗り、南太平洋地域を調査研究する機会を得、地質学・生物物理学について豊富な知識と着想を携えて36年に帰国した。翌年にはビーグル号による調査で得た知識を説明する理論として、進化の考えに到達したが、進化の機構をめぐるさまざまな模索を試み、38年に自然選択による進化学説をほぼ完成した。しかし、十分な資料の収集と理論の彫琢を期して長い間公表には踏みきらず、1859年になってようやく本書を刊行した。
本書は進化論を確立した著作として生物学史上最も重要な古典とされている。初版出版の翌年にドイツ語に訳されたのをはじめとして各国語に翻訳され、科学者や知識人の間に進化の思想が急速に普及した。また、本書は生物学だけでなく人類の思想にはかり知れぬ影響を与えた。出版後十数年間は売れ行きがよくなかった本書が民衆に歓迎されるようになったのは、進化の思想が産業資本主義の発展期における自由競争の理念と一致したためであり、進化論への宗教的反対は、ダーウィンが本書で回避した人間の進化の問題が原因となって起きたものであった。
A manual on extracting teeth : founded on the anatomy of the parts involved in the operation; the kinds and proper construction of the instruments to be used; the accidents liable to occurfrom the operation, and the preper remedies to retrieve such accidents
『抜歯学入門』
本書はロバートソン(1751-1826)による抜歯についてのマニュアルであり、抜歯に必要な解剖学の知識や手術用具、手術により発生しやすい事故とその処置などが記されており、5年後には第2版が出版されている。
Dental materia medica
『歯科薬物学』
ホワイト(1826-91)は、陶歯の製造を手始めに歯科器材メーカーとなったS. S. White社の創業者として有名なサミュエル S. ホワイト(Samuel Stockton White)の弟であり、1873年から雑誌"Dental Cosmos"の主筆を務めた。
本書では、当時使用されていた129種の歯科用薬物について、その特性や使用法等を解説している。
Leçons de pathologie expérimentale
『実験病理学』
フランスの生理学者であるベルナール(1813-78)は、21歳のとき劇作家をめざしてパリに出たが、まもなく医学に転じ、マジャンディー(Francois Magendie)の弟子となり、生理学研究に専念した。1854年にソルボンヌに新設された生理学講座を担当したのち、コレージュ・ド・フランスの正教授となり、その後フランスアカデミーの会員、そして、69年には科学者としては異例の上院議員に指名された。彼の業績は、生理学の多くの分野にわたっているが、重要な研究は膵臓機能の解明、肝臓のグリコーゲン合成機能とそれに関連した糖尿病の原因解明、および交換神経の血管運動支配の発見などである。これらがすべて、粗末な実験室で巧みな方法を用いて行われ、精細な結果を得ている点に実験家としての彼の卓抜さがあり、実験医学の基礎を確立した功績は高く評価されている。
Mechanical dentistry in gold and vulcanite : arranged with regard to the difficulties of the pupil, mechanical assistant, and young practitioner
『金と蒸和ゴムの歯科補綴学』
イギリス人でプリマスの開業歯科医であったバルクウィル(1837-1921)は、咬合器の設計基準となるバルクウィル角の発見者として有名であるが、咬合の原理を研究し、その成果を1866年にロンドンで開かれたイギリス歯科医学会で発表した。彼は当時すでに顎関節の複雑な動きやその役割をはじめ、咬合彎曲についても、他の多くの知識とともに知っていた。咬合器の完成者として有名なギージー(Alfred Gysi)は、46年後の1912年にこの咬合問題の先駆者の功績を大いにほめたたえている。バルクウィルは2冊の著書を出版しているが、本書は学生や若い臨床家のための歯科補綴学のハンドブックとして書かれている。
A treatise on oral deformities as a branch of mechanical surgery
『口腔の奇形』
「歯科矯正学の父」と呼ばれるキングスレー(1829-1913)は、1852年にニューヨークに移り、しばらくして自分の診療所をもち大成功をおさめた。その後、陶歯を改良して万国博覧会で金賞を受賞したり、人工口蓋帆を考案したりすると同時に、歯科矯正学の研究に打ち込んだ。また、ニューヨーク歯科大学の共同創設者となり、1871年にはボルチモア歯科大学から名誉博士号を受けた。1871年から歯列矯正に関する論文を発表しはじめ、1877年には、今日も彼の名で呼ばれている咬合跳躍法(jumping plane)について発表し、その豊富な知見を集成して1880年に本書を刊行した。
本書は、過去の一切の知識を網羅したアメリカ最初の歯科矯正学の専門書となっており、本書の刊行以降、歯科矯正学は歯科医学において専門分野のひとつとして認められるようになった。
20世紀
Descriptive anatomy of the human teeth
『歯の解剖学』
ブラック(1836-1915)は、歯科保存学の先駆者であるだけでなく、歯牙解剖学や歯科病理学などの研究に、また各種の歯科用器械の改良と考案に、さらに歯学教育者として、歯科学全域に及ぶ活動を展開しており、「ブラックの前にブラックなし、ブラックの後にブラックなし」と評された。彼は独学で歯科学を修めて開業したのち、一連の研究論文によって注目を浴び、ミズーリ歯科医学校やシカゴ歯科医学校の教授を経て、ノースウェスタン大学の教授となり、1897年から死去するまでは歯学部長を務めた。
本書は彼の主著のひとつで、初版は1890年に出版されており、その後も版を重ねた。
A work on operative dentistry
『歯科治療学の研究』
ブラック(1836-1915)の卓越した永続的な功績は、窩洞形成の体系を作ったことにある。彼は、1891年より齲蝕の病理に裏付けられた窩洞形成の理論を発表し、画期的な予防拡大法を解き、独自の窩洞分類法を提唱して、充填治療システムを確立した。また、理工学実験から平衡性合金となるアマルガム処方を発表した。以上のような彼のライフワークをまとめて出版したのが本書である。
本書は、上巻“The pathology of the hard tissues of the teeth”と下巻“The technical procedures in filling teeth”からなっており、20世紀の保存修復学の主流を築いた名著といわれている。1914年には、ブラックの弟子でウィーン大学教授のピヒラー(Hans Pichler)によってドイツ語に訳されている。
A work on special dental pathology : devoted to the diseases and treatment of the investing tissues of the teeth and the dental pulp, including the sequelae of the death of the pulp; also, systemic effects on mouth infections, oral prophylaxis and mouth hygiene
『歯科病理学持論』
ブラック(1836-1915)が死の数ヵ月前に出版した本書は、歯科病理学における彼の生涯にわたる研究活動を集大成したものであり、彼の死後も版が重ねられた。
1916年のアメリカ歯科医師会総会では、ブラックの多大な功績を記念するための委員会が設けられ、1918年にシカゴのリンカーン公園に彼の記念像が建てられた。